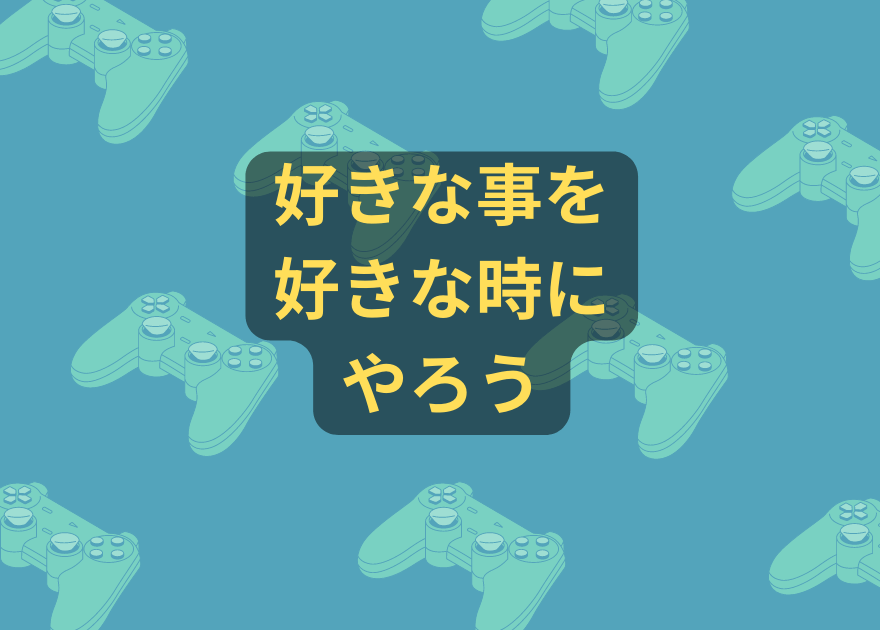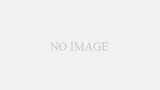先日、高校時代の同級生と偶然会い、昔話をする中で教育に関する話題にもなったので(久しぶりにとても楽しい時間でした)、今日は息子たちの事ではなく、自分の事を振り返りつつ、教育について少し考えたいと思います。
偏差値競争を経験
私たちの世代は「団塊ジュニア」「第二次ベビーブーマー」と呼ばれる、とても人口の多い年代でした。
高校時代は、バブルの絶頂期だったらしく(学生の私たちは直接わかりませんでしたが)、「頑張って勉強しなさい。そして、良い大学に入り、良い会社に就職しなさい。そうすれば一生安泰だから」と言われていました。
人口が多いので、勢いがあったと思いますが、その分「ライバルも多い」状態でした。
多くのライバルに勝つために、より試験で高得点を取らなければならない状況にあり、まさに偏差値競争の激戦時代だったと思います。
ただ、私たちは地方の公立高校だったので、都会の私立ほどではなかったと思います。
そして、先日同級生K君が言っていた事で、私も強く共感したことが『あのとき(高校時代)何も考えずに、ただ大学進学を競っていたよね。そして、大学入ったらバブル崩壊で、就職氷河期に直面し・・・』と。
息子さんが不登校
これは実際その通りなのですが、同年代でこのような話を直接する人が私の周りにいなかったので、少し驚きながら共感し、さらにいろいろ話をすると「K君の息子さんが不登校だった」ことを教えてくれました。
我が家と似た状況であり、何となくそれで合点がいきました。
現在息子さんは工業高校に通っており、電子機器等の使用を楽しみながら過ごしているとのことです(数学・国語等の科目は嫌いのようですが、工業高校のためか、そのような一般受験科目は少なく、この点も高校に通えている一因だろうとK君は言っていました)。
大学進学は考えていない様です。
偏差値教育の2つの弊害
そして、本日のタイトルにも上げた本題の”偏差値教育の弊害”についてですが、主に2つあると考えています。
1つ目はK君も話していた「良い大学に入っても、必ずしも良い仕事に就けるとは限らない」です。
さらに、今の時代は「良い会社に入ったとしても、定年まで勤められるかわからない(リストラされるかもしれないし、会社が倒産するかもしれない)」もありますし、もっと言えば「そもそも”良い会社とはどんな会社か?”はっきりわからない」という事です。
しかし、80歳の私の母は未だにこの考えに同意できないようです(過去記事「私の母の古い固定観念に驚く」)。
2つ目は、私の職場の新人などを見ていて感じるのですが「偏差値競争で勝ったのだから、俺はスゴイ」と勘違いし、『人を偏差値で評価しがちな人間になる』点です。
テストの点数は良かったかもしれませんが、仕事に於いてはそれはほぼ関係ありません。
長年勤務しているパートの人のほうが圧倒的に仕事ができる状況はザラにあるのですが、「俺は勝者で、パート職員は敗者」と思っている発言・振る舞いをする若者がいます。
それを見るたびに「そこでマウントとっても自分の小ささを露呈しているだけだよ・・」と思いますが、私が言ったところで本人は納得しないでしょう。
これは仕事をする上で本人にとってデメリットになっています。
全員がこのようになるわけでは無いでしょうし、勉学を競う利点もありますが、本日は偏差値教育の弊害として私が感じた2つについて述べました。
教育はなかなか難しいですね。