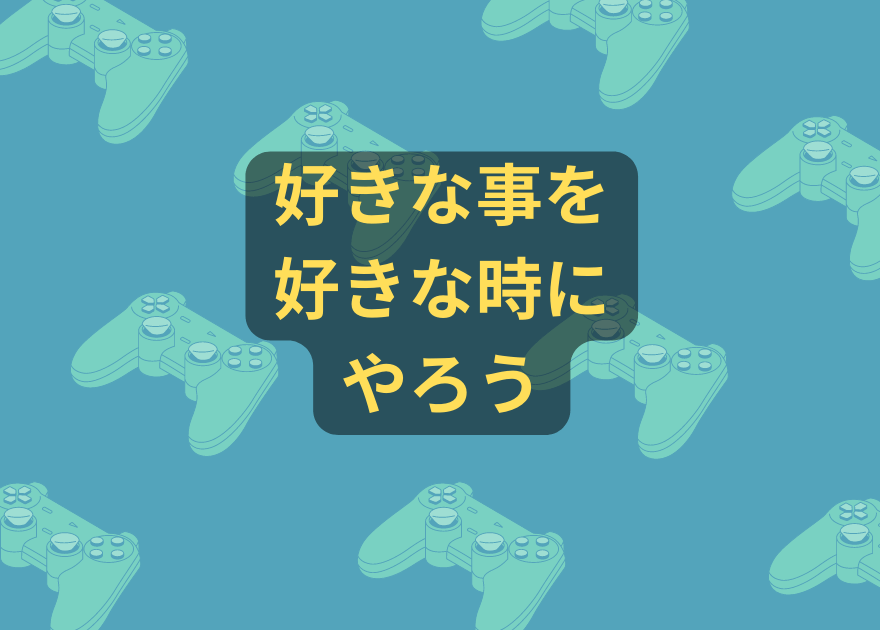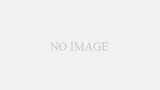不登校の次男が3月に中学を卒業しました(過去記事「次男は一日も登校せずに中学を卒業」)。
教育を受けていない次男
小学校6年間+中学校3年間の合計9年間の義務教育のうち、3分の2(6年間)が不登校で学校に通いませんでした。
つまり、初めの3分の1だけ登校して、義務教育修了という扱いになったわけです。
これについては色々思う所はありますが、不登校の期間の後半は中学校からも登校を促されることも無くなりましたので、「放っておいてくれるのが一番助かる」という気持ちが大きかったです。
かといって、現在も増え続ける不登校数に対して、国の対応が次男と同様で良いとは思いません。
現行の小中学校ではもはや不登校への対応は不可能なわけで、何かしらの変革が必要です。
遅い改革と、早い子供の成長
私は「通信制」中学校を国(文科省)が正式に認可することが良いと思っているのですが、文科省はこれを否定しています(過去記事「通信制”中学”を文科省(国)は認可していない②」)。
この文科省の姿勢は残念ですが、文科省が進めている「学びの多様化学校(不登校特例校)・夜間中学」を増やす政策については、期待できる点もあります(過去記事「学びの多様化学校(不登校特例校)が通信制中学校誕生につながる?」)。
とは言え、効果を表す以上に不登校の児童・生徒数が増加するでしょうから、行き詰まる可能性が高いだろうとも思っていますが。
ゆっくりと政策を実施していても、子供はあっという間に義務教育を終える事を今回次男の中学卒業で感じました。
ですので「次男が義務教育終えたから私にはもはや関係ない」ではなく、これから義務教育を受ける子供のためにも私ができることを微力ながらやっていきたいと今は思っています。
心理士さんに感謝
現在このように私が思えるようになった一つの理由は、次男の不登校について関わってくれた心理士さんのサポートが大きかったからです。
学校・自治体のこども課・児童精神科など、不登校初期(~中期)にはいくつかの支援を受けましたが、その中で我が家にとって最も助かったのが心理士さんでした。
とは言え、次男が心理士さんと会う事は一度もなく(次男が行きたがらなかった)、会って話をしていたのは妻だけです。
不登校の子供本人ももちろんつらいですが、親もつらいです。
私も次男が不登校になった頃は、本当に「次男の人生終わった」と思ってしまったものです。
そのような苦しい親の気持ちを救ってくれたのが心理士さんで、妻は先月まで毎月、心理士さんのところに通っていました。
最近は雑談するだけともなっていたようですが、会話をすると心がスッキリするらしく、約5年間お世話になりました。
そして、この貴重な面談も次男の義務教育修了をもって、最後となりました。
妻は本当に感謝をしており、私も妻から面談内容を教えてもらうたびに「その心理士の先生、すごいね」と感じ、私自身も勇気をもらえることが多かったです。
このように不登校の家庭を支えてくださったことに感謝しつつ、今後は私もサポートする側になりたいと思い始めています。
心理士さん、本当にありがとうございました🙇♂️
※次回から投稿の曜日を、水曜&日曜の週2回に変更予定です(今までは金曜&日曜)。引き続きよろしくお願いいたします。